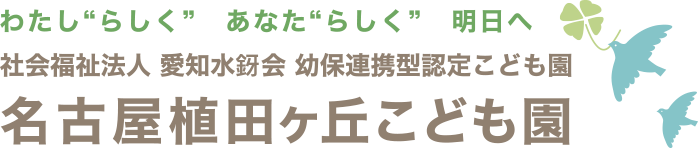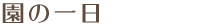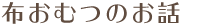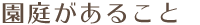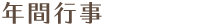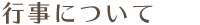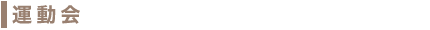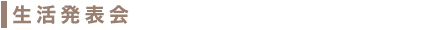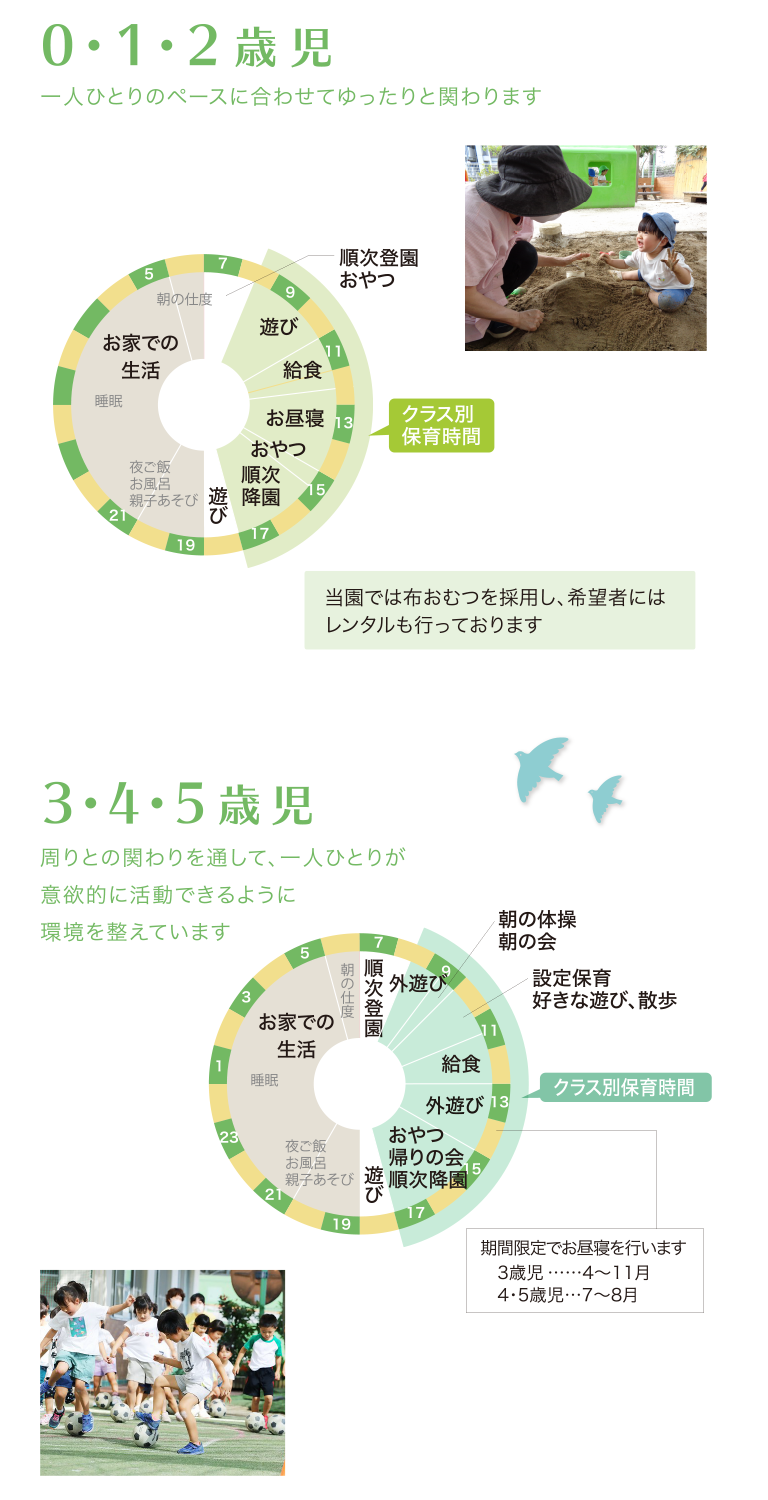
こども園では日々、集団保育の中で私たち保育者が子どもたちのお世話をしています。
子どもたちの日々の生活は「食事」「睡眠」「排泄」「あそび」という4つのサイクルで展開していきます。私たち保育者も、当然、このサイクルのすべてにかかわっています。
自分大好き みんな大好き―
保育を通して、子どもたちにこのことを伝えていきたいと一人ひとりを大切に見つめています。
先ほど挙げた子どもたちの4つのサイクルを見てもらえるとご理解いただけると思いますが、実はこの4つのサイクルの中で「排泄」の回数が最も多いのです。そして、唯一保育者と1対1になれる時間なのです。
子どもたちの日々の生活は「食事」「睡眠」「排泄」「あそび」という4つのサイクルで展開していきます。私たち保育者も、当然、このサイクルのすべてにかかわっています。
自分大好き みんな大好き―
保育を通して、子どもたちにこのことを伝えていきたいと一人ひとりを大切に見つめています。
先ほど挙げた子どもたちの4つのサイクルを見てもらえるとご理解いただけると思いますが、実はこの4つのサイクルの中で「排泄」の回数が最も多いのです。そして、唯一保育者と1対1になれる時間なのです。

国が定める保育園・こども園の保育者の配置基準は、最も多く配置できる0歳児でさえ、子ども3人に対して1人です。
日々の保育の中で、一人ひとりとしっかり向き合う時間をつくることは難しいのが実情です。
しかし・・・その中にあって、唯一おむつ交換の時間は1対1で向き合う大切な時間。
目と目を合わせることができる時間。
「いっぱい出たね」「替えて心地よくなった?」目を見ながらやさしく語りかける保育者の言葉。
そこは子どもたちと1対1で心を通い合わせることができる大切な機会です。
そして、この1対1での心のふれあいを通して、子どもたちが「大切にされている」という自己肯定感を芽生えにつながっていくと捉えています。
紙おむつは非常に便利で快適です。
しかし・・・濡れてしまっても、汚れてしまっても不快であるということを感じにくいのです。
「濡れて不快だろうな・・・」この保育者の想いこそ大切にしたいと思っています。
子どもたち一人ひとりの気持ちに想いを馳せること。
それこそが子どもたち自身が大切にされていると感じる第一歩なのではないでしょうか。
私たち名古屋植田ケ丘こども園では、満2歳になる頃から個々の発達を見つめながら排泄の自立につなげていきます。
「おしっこを自分で溜めて出せた!」今までできなかったことが自分でできるようになること・・・それが自立の芽生えです。
自分のことを大切に想ってくれる保育者の存在こそが、子どもたちの自己肯定感の確立に大きな影響を与えていくものと捉えています。
日々の保育の中で、一人ひとりとしっかり向き合う時間をつくることは難しいのが実情です。
しかし・・・その中にあって、唯一おむつ交換の時間は1対1で向き合う大切な時間。
目と目を合わせることができる時間。
「いっぱい出たね」「替えて心地よくなった?」目を見ながらやさしく語りかける保育者の言葉。
そこは子どもたちと1対1で心を通い合わせることができる大切な機会です。
そして、この1対1での心のふれあいを通して、子どもたちが「大切にされている」という自己肯定感を芽生えにつながっていくと捉えています。
紙おむつは非常に便利で快適です。
しかし・・・濡れてしまっても、汚れてしまっても不快であるということを感じにくいのです。
「濡れて不快だろうな・・・」この保育者の想いこそ大切にしたいと思っています。
子どもたち一人ひとりの気持ちに想いを馳せること。
それこそが子どもたち自身が大切にされていると感じる第一歩なのではないでしょうか。
私たち名古屋植田ケ丘こども園では、満2歳になる頃から個々の発達を見つめながら排泄の自立につなげていきます。
「おしっこを自分で溜めて出せた!」今までできなかったことが自分でできるようになること・・・それが自立の芽生えです。
自分のことを大切に想ってくれる保育者の存在こそが、子どもたちの自己肯定感の確立に大きな影響を与えていくものと捉えています。
私たちの園には広い園庭があります。
一見何でもない光景ですが、
子どもたちにとって「園庭がある」ということはきっと大きな意味をもっているのだと思っています。
子どもたちは、あそびを通して様々なことを獲得していきます。
それは、友情であったり、大好きな先生との心の通い合いだったり、
時に挑戦の場であったり、友との語らいの場、大切な友と友情を確かめ合う場だったり・・・。
子どもたちにとって、まさに「学びの庭」「成長の場」そのものなのです。
保育室を飛び出して、「自分たちの庭」で仲間と心置きなく思いっきり自分を表現できる場。
砂場で作った自分たちの作品・・・
「今日はここまでね、また明日続きをしよう!」ということができるのは、実は「自分たちの庭」があるからこそです。
だからこそ遊びを発展・継続させることができるのです。
心と身体の形成にもっとも大きな影響を与えるもの。
それは保護者のあたたかなまなざし、私たち保育者の存在、地域の人との交流、そして何より友と心置きなく過ごす場。
その一コマ一コマは、園庭と共に子どもたちの脳裏にいつまでも生き続けるのだと考えています。
一見何でもない光景ですが、
子どもたちにとって「園庭がある」ということはきっと大きな意味をもっているのだと思っています。
子どもたちは、あそびを通して様々なことを獲得していきます。
それは、友情であったり、大好きな先生との心の通い合いだったり、
時に挑戦の場であったり、友との語らいの場、大切な友と友情を確かめ合う場だったり・・・。
子どもたちにとって、まさに「学びの庭」「成長の場」そのものなのです。
保育室を飛び出して、「自分たちの庭」で仲間と心置きなく思いっきり自分を表現できる場。
砂場で作った自分たちの作品・・・
「今日はここまでね、また明日続きをしよう!」ということができるのは、実は「自分たちの庭」があるからこそです。
だからこそ遊びを発展・継続させることができるのです。
心と身体の形成にもっとも大きな影響を与えるもの。
それは保護者のあたたかなまなざし、私たち保育者の存在、地域の人との交流、そして何より友と心置きなく過ごす場。
その一コマ一コマは、園庭と共に子どもたちの脳裏にいつまでも生き続けるのだと考えています。
 |
入園式★ 進級式 童話会 個人懇談会★ 親子ふれあい会(4・5歳児)★ クラス懇談会★ |
|---|
 |
プールあそび 科学館見学(5歳児) 七夕 |
|---|
 |
運動会★ 個人懇談会★ 園外保育 |
|---|
 |
クリスマス会 もちつき大会 人形劇 節分 生活発表会★ 個人懇談会★ お別れ遊ぼう会 ひなまつり 卒園式★ |
|---|
その他…体育あそび(3・4・5歳児)、誕生会、絵画展
希望により、試食・保育参観、保育体験を行っています
園は1年間の中で、様々な行事を計画しています。
行事は、季節を感じられるもの、家庭では経験できないもの、伝統的なもの、地域との交流、
発達に合わせたものなど様々な観点で計画しています。
その中でも、保護者に参観していただきたい行事として、運動会と生活発表会という2つの大きな行事があります。
これらの行事を通しながら、我が子の成長を感じられたらと位置づけています。
行事は、季節を感じられるもの、家庭では経験できないもの、伝統的なもの、地域との交流、
発達に合わせたものなど様々な観点で計画しています。
その中でも、保護者に参観していただきたい行事として、運動会と生活発表会という2つの大きな行事があります。
これらの行事を通しながら、我が子の成長を感じられたらと位置づけています。
運動会は毎年同じ種目のシンプルなものです。 保護者に参観していただきます。
子どもたちが、年齢が上がるごとに身体機能が 発達していくこと、仲間関係が育っていることな どをご覧いただいています。大きくなったら、あ んなことができるのだなといった成長の見通しは、 明日の成長の望みに繋がっていきます。子どもた ちも、お兄ちゃんやお姉ちゃんの様々な種目に憧 れ、好きな遊びの中で自分たちもあんな風にやり たいと、運動会前後から鉄棒の技に挑戦したり、 リレーごっこや組み立て体操ごっこが盛んになり、 1年後の運動会に向かっていくのです。
こうして年上の子どもたちへの憧れから、その技を自分たちのものにしたいと、コツコツと好き な遊びを通して成長していきます。
生活発表会は、保護者に参観していただきます。3歳頃になると、自分が動物などになりきったり、少しずつイメージを持って友達と遊べるようになっていきます。
絵本のお話の世界に入って楽しむことができるので、3歳児クラスになると簡単な言葉遊びから始まって、年長の5歳児のクラス全体で作り上げる劇遊びと、歌と楽器遊びを披露します。
絵本のお話の世界に入って楽しむことができるので、3歳児クラスになると簡単な言葉遊びから始まって、年長の5歳児のクラス全体で作り上げる劇遊びと、歌と楽器遊びを披露します。
保護者の皆さんに参観してもらう前提から始まるのではなく、ファンタジーの世界に子どもたちが入り込み、幼児ならではの想像遊びをたっぷり楽しむことを目的にしています。 つまり、生活発表会のための練習ではなく、あくまでも、子どもたちの遊びの世界、日々の保育の延長にあるものです。
運動会も生活発表会も、その行事当日の保護者参観のために練習するのではなく、取り組みの一日一日は、遊びの連続です。
「あー、おもしろかった!」
「もっとやりたい!」
「また、明日もやろうね」といった声が聞ける
遊びの時間になるようにしています。
運動会も生活発表会も、その行事当日の保護者参観のために練習するのではなく、取り組みの一日一日は、遊びの連続です。「あー、おもしろかった!」「もっとやりたい!」「また、明日もやろうね」といった声が聞ける遊びの時間になるようにとらえています。
また、これらの行事は、どこかの会場を借りるのではなく、園内で行っています。保護者の皆さんには、たくさんの観衆で狭くて、申し訳ないのですが、子どもの視点からすれば、毎日遊び慣れたところだからこそ、遊びの延長としての行事で保護者の参観してもらうことを自然な流れの中で迎えていきます。「劇遊びごっこが面白くなってきたから、おうちの人に見てもらおうか。」「縦はあの位置に移動して3人組になってタワーを作ろう。」「このカーブにさしかかったら速さを緩めて、あとは全速力でゴールだ!」などと初めての場所での保護者参観行事を迎えるのでなく、場所見知りもせず、ほとんどの子どもが自分の素敵な姿を保護者の皆さんにお見せすることができるのです。
そして子どもたちにとって運動会や生活発表会がゴールではなくて、終わった後も余韻を楽しんだり、
新たな挑戦・あそびの展開へとつながっていくのです。
行事というのは、保護者の方に見せるために存在するものではなく、子どもたちにとって、あそびの世界の延長にあるものと私たちは位置付けています。
また、これらの行事は、どこかの会場を借りるのではなく、園内で行っています。保護者の皆さんには、たくさんの観衆で狭くて、申し訳ないのですが、子どもの視点からすれば、毎日遊び慣れたところだからこそ、遊びの延長としての行事で保護者の参観してもらうことを自然な流れの中で迎えていきます。「劇遊びごっこが面白くなってきたから、おうちの人に見てもらおうか。」「縦はあの位置に移動して3人組になってタワーを作ろう。」「このカーブにさしかかったら速さを緩めて、あとは全速力でゴールだ!」などと初めての場所での保護者参観行事を迎えるのでなく、場所見知りもせず、ほとんどの子どもが自分の素敵な姿を保護者の皆さんにお見せすることができるのです。
そして子どもたちにとって運動会や生活発表会がゴールではなくて、終わった後も余韻を楽しんだり、
新たな挑戦・あそびの展開へとつながっていくのです。
行事というのは、保護者の方に見せるために存在するものではなく、子どもたちにとって、あそびの世界の延長にあるものと私たちは位置付けています。